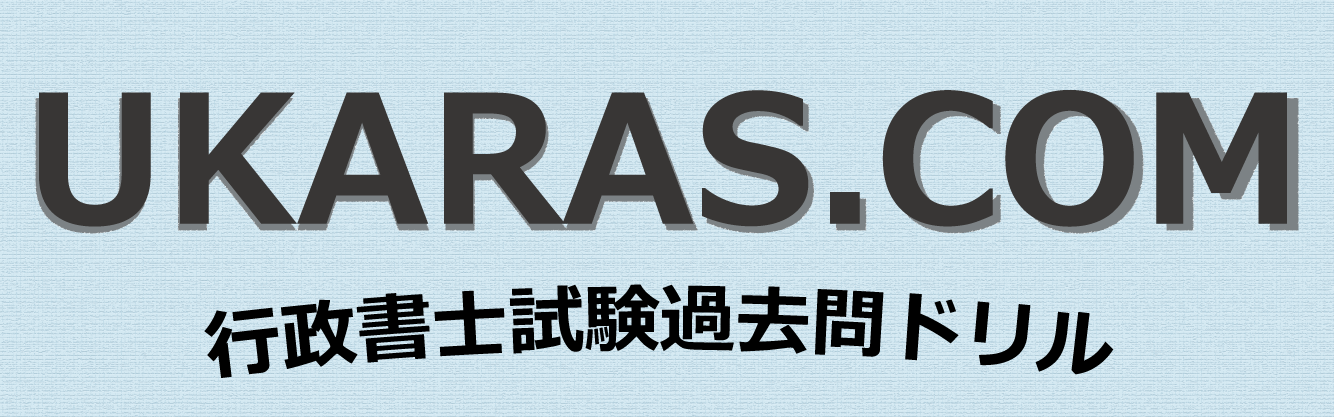解答 行政書士試験 平成19年21問
地方自治法
○:3.地方自治法14条に基づく地方議会の条例制定権限は、当該事務が自治事務である場合のみならず、法定受託事務である場合にも及ぶ。
○:3.地方自治法14条に基づく地方議会の条例制定権限は、当該事務が自治事務である場合のみならず、法定受託事務である場合にも及ぶ。
問21
条例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.自治体の処理する事務のうち、自治事務に関しては法律で内容的な定めを設けることはできず、このような定めは法定受託事務に限定される。
☓:2.自治事務に関する条例は法律の個別授権を受けることなく定めることができるが、私人の権利義務に直接かかわる規定は、必ず法律の個別授権を受けなければならない。
○:3.地方自治法14条に基づく地方議会の条例制定権限は、当該事務が自治事務である場合のみならず、法定受託事務である場合にも及ぶ。
☓:4.法律の規定を具体化するのは、地方公共団体の機関が定める規則等であり、具体化の規定が条例に置かれることはない。
☓:5.法律により規制の対象とされている事項について、法律の明示の授権がなくとも、規制の適用を除外する特例措置を条例により設けることは可能である。
解説
1.妥当でない。
憲法92条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と規定しており、これに対応するべく地方自治法では「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。」(同法第2条11項)や「法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。」と要請されているにすぎず、自治事務に関して法律で内容的な定めを設けることはできない旨の定めは存在しない。
したがって、法定受託事務はもとより、自治事務においても、法律で内容的な定めを設けることはできる。
2.妥当でない。
地方自治法14条2項では「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 」としており、私人の権利義務に直接かかわる規定であっても、必ずしも法律の個別授権を受けなければならないものではない(最大判昭和37年5月30日)。
したがって、前半は正しいが、後半が誤りである。
3.妥当である。
普通地方公共団体は、自治事務・法定受託事務どちらについても、条例を制定することができる(地方自治法14条1項、2条2項)。
4.妥当でない。
地方公共団体の議会の条例制定権(地方自治法第14条1項)及び地方公共団体の長の規則制定権(同法第15条1項)では、どちらも「法令に違反しない限りにおいて」という制限があるだけなので、どちらにも法律の規定を具体化する規定を置くことができる。
実際、公衆浴場法第2条3項では「公衆浴場の設置の場所の配置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。」としており、このような法律で条例に委任しているものは数多くある(建築基準法第49条、消防法第9条、旅館業法第4条2項など)。
なお、このような法律の委任を受けた条例を委任条例というのに対し、法律の委任を受けてない条例を自主条例という。
5.妥当でない。
地方自治法第14条1項は、法令に違反しない限りにおいて、地方公共団体の議会の条例制定権を認めているにすぎず、法律により規制の対象とされている事項について、規制の適用を除外する特例措置を条例により設けることは、当該法律に抵触・矛盾することになるため、法律の明示の授権がなければ許されない(徳島市公安条例事件:最大判昭和50年9月10日参照)。
この問題の成績
まだ、データがありません。