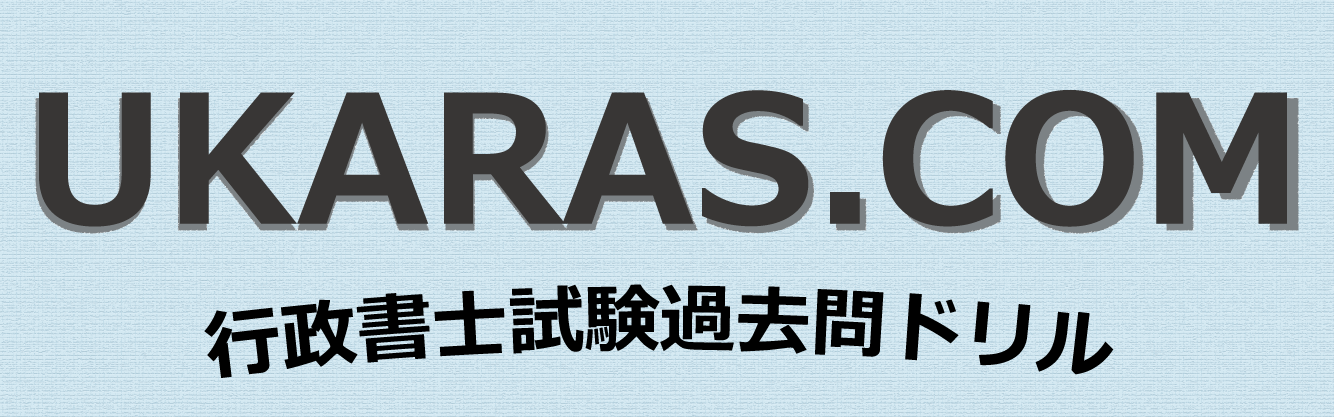解答 行政書士試験 平成19年25問
地方自治法
○:2.二つ
○:2.二つ
問25 地方自治法の定める住民監査請求、住民訴訟に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア、住民監査請求は事務監査請求とは異なり、当該地方公共団体の住民に限らず、何人であっても一人で提起することができる。
イ、住民訴訟を提起するには、原則として住民監査請求を経ている必要があり、これを住民監査請求前置(主義)という。
ウ、住民訴訟においては、当該地方公共団体の執行機関または職員に対して行為の全部または一部の差止めの請求をすることは認められていない。
エ、住民訴訟の対象は、当該地方公共団体の長等の違法な財務会計上の行為または怠る事実であるが、不当な行為または怠る事実は対象とできない。
オ、住民監査請求にも住民訴訟にも期間の制限があり、これを徒過すると提起することはできなくなる。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.一つ
○:2.二つ
☓:3.三つ
☓:4.四つ
☓:5.五つ
解説
ア.誤り。
住民監査請求は、事務監査請求における有権者の50分の1の連署という要件がないため(地方自治法第75条以下)、一人で行うことができるが、当該地方公共団体の住民であることが必要である(地方自治法242条1項)。
イ.正しい。
住民訴訟は、住民監査請求前置(主義)を採り、住民監査請求を経ていることが原則として必要である。
なお、住民監査請求をしたのに、監査または勧告が行われるべき期間内(請求があった日から60日以内)になされない場合は、監査の結果が出る前でも住民訴訟を提起できる(地方自治法第242条の2第1項)。
ウ.誤り。
住民訴訟は、4つの類型が法定されており、(1)「差止めの請求」、(2)「取消し又は無効確認の請求」、(3)「怠る事実の違法確認の請求」、(4)「相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを求める請求」がある(地方自治法第242条の2第1項各号)。
したがって、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して行為の全部又は一部の差止めの請求をすることは認められている(地方自治法第242条の2第1項1号)。
エ.正しい。
住民訴訟の対象となるのは、「違法な行為または怠る事実」であり、住民監査請求で認められている「不当な行為または怠る事実」は除外されている(地方自治法第242条の2第1項)。
オ.正しい。
監査請求は、当該行為のあった日又は終わった日から原則として一年という期間制限がある(地方自治法第242条2項)。
また、住民訴訟についてもそれぞれの訴訟事案における起算日から三十日以内という出訴期間がある(地方自治法第242条の2第2項)。 そして、これを徒過すると原則として提起することはできなくなる。
この問題の成績
まだ、データがありません。