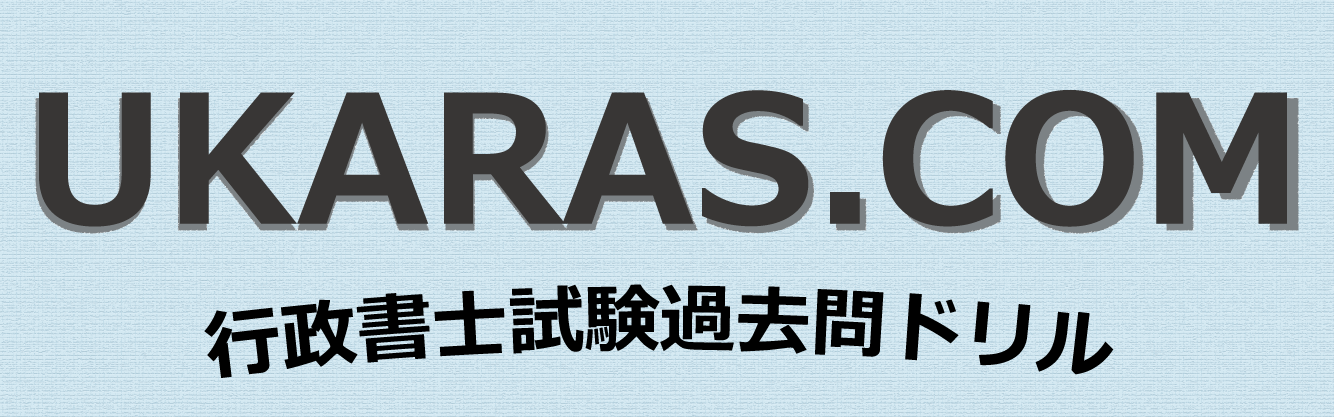解答 行政書士試験 平成24年60問
一般知識 文章理解
○:1.(Ⅰ)イ (Ⅱ)ア (Ⅲ)エ (Ⅳ)ウ
○:1.(Ⅰ)イ (Ⅱ)ア (Ⅲ)エ (Ⅳ)ウ
問60 本文は、川瑞康成の小説『伊豆の踊子』に関する文章である。
伊豆を徒歩旅行中の主人公(旧制第一高等学校の学生)は旅芸人の踊子達と道連れとなった。
冒頭に引用されている場面(下線を施した部分)は、別々の宿に泊まった翌朝、朝風呂に入って主人公を対岸の共同浴場から見つけた踊子の様子を描いたものである。
本文中の空欄[Ⅰ]~[Ⅳ]に当てはまるものの組合せとして、適切なものはどれか。
仄暗い湯殿の奥から、突然裸の女が走り出して来たかと思ふと、脱衣場の突鼻に川岸へ飛下りさうな格好で立ち、両手を一ぱいに伸して何か叫んでゐる。手拭いもない真裸だ。それが踊子だつた。若桐のやうに足のよく伸びた白い裸身を眺めて、私は心に清水を感じ、ほうつと深い息を吐いてから、ことこと笑つた。子供なんだ。
(中略)主人公が、コトコト笑った背景を確認しておこう。
今から八〇年も前の話。旅芸人は、かなり差別的に扱われ、この話も、踊子は、時に身を売ることだってある、という設定で書かれている。事実、「茶店の婆さん」も、主人公に向かって、踊子たちは、「お客があればあり次第、どこにだつて泊るんでございますよ」と、ずいぶんなことを平気で言っている。
その婆さんの「甚だしい軽蔑を含んだ」言葉に、主人公は、「それならば、踊子を今夜は私の部屋に泊らせるのだ」と、義憤にかられたりする。一晩だけでも、守ってやるつもりなのである。けれども、踊子は、ほかの芸人たちと共に宿屋の座敷に呼ばれ、三味線にあわせて、太鼓をたたき続ける。その太鼓の音がとだえ、夜が静まりかえると、主人公は、「踊子の今夜が汚れるのであらうか」と思って、悶々とするのである。
そして、明けた朝。
主人公は、旅芸人の一行の男と、一緒に風呂に行く。そのあとに、前に引用したシーンが続く。
それで、主人公は、自分が想像していたことなど、まったく起こらなかったことを瞬時に悟るのである。「子供なんだ」という思いには、主人公の、安堵をはじめとした、さまざまに重なる気持ちがこもっている。
その思いで、主人公は、「ことこと笑つた」のである。(中略)
主人公が、「けたけた」笑ったらどうか。これはどうも、ちょっと軽すぎる。踊子のことを何かバカにしているようなニュアンスさえ感じる。
「けらけら」笑ったらどうか。明るい感じは、よい。好意も感じる。しかし、明るすぎないか。落ち着きがない。ちょっと品もない。
「からから」笑ったらどうか。朗らかである。心地よい。これは、悪くない。けれども、やはり明るすぎる。快活すぎる。主人公の、[Ⅰ]は何だったのか、といぶかしくなる。
「あはあは」も同じ。無邪気だが、明るすぎ。(中略)
「ころころ」笑ったらどうか。これは、かなり近い。悪くない。しかし、ちょっと幼すぎるのではないか。
「がはがは」「げたげた」「げらげら」。論外。声が大きすぎ。品もなさすぎ。
今までのところから得られるのは、軽く、明るく、しかし、はじけすぎず、[Ⅱ]を表わしている、というところであろう。
もう少し、考え続けてみる。
「にこにこ」笑ったらどうか。これも悪くない。踊子への、優しいまなざしを感じる。しかし、まあ、ありきたりである。また、これは、踊子への直接的なまなざしは表現できるが、[Ⅲ]が、どこか感じられない。また、これには、声がない。
「くすっ」と笑ったらどうか。これも悪くない。優しいまなざしと、好意。けれども、これでは、瞬間的すぎる。[Ⅳ]が表現しきれていない。この点、「にこっ」と笑う、も同じである。
(小野正弘『オノマトペがあるから日本語は楽しい 擬音語・擬態語の豊かな世界』より)
ア 穏やかな好意
イ あの悶々とした気持ち
ウ 自分でも押さえきれないほど、こみ上げてくる笑い
エ 自省というか、内観というか、とにかく、自分自身の気持ちの深まり
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.(Ⅰ)イ (Ⅱ)ア (Ⅲ)エ (Ⅳ)ウ
☓:2.(Ⅰ)イ (Ⅱ)ウ (Ⅲ)エ (Ⅳ)ア
☓:3.(Ⅰ)エ (Ⅱ)ア (Ⅲ)イ (Ⅳ)ウ
☓:4.(Ⅰ)エ (Ⅱ)ウ (Ⅲ)ア (Ⅳ)イ
☓:5.(Ⅰ)エ (Ⅱ)ウ (Ⅲ)イ (Ⅳ)ア
解説
[Ⅰ]:イ
まず、主人公が「ことこと」笑った背景をまとめると、
主人公は踊子を一晩だけでも守ろうとしたが、結局そんなことはできず「踊子の今夜が汚れるのであらうか」と思って、悶々とした夜をすごす。
ところが、翌日浴場で裸で無邪気に走る姿を見て、杞憂であったと悟り、安堵をはじめとした、さまざまに重なる気持ちから、「ことこと」笑ったのである。
そうすると、「主人公の、[Ⅰ]は何だったのか、」という文において[Ⅰ]に入るのは、前の晩の苦しんだ感情を表す言葉が適当である。
したがって、「あの悶々とした気持ち」が入る。
[Ⅱ]:ア
[Ⅱ]の前は、「今までのところから得られるのは、」となっており、その後には、これまでの考察で良い点が並んでいるため、[Ⅱ]もそれと同様のものが入る。
そこで、それまでの良い点を抜き出すと、「けらけら」の『明るい』『好意』、「からから」の『朗らか』『心地よい』、「あはあは」の『無邪気』がある。
そして、これを文章に当てはめると
「軽く(=『無邪気』に対応)、明るく(=『明るい』に対応)、しかし、はじけすぎず[Ⅱ](=『朗らか』『心地よい』『好意』に対応)を表わしている』
となる。
『朗らか』『心地よい』『好意』に対応するのは、アの「穏やかな好意」しかない。
[Ⅲ]:エ
[Ⅰ]の背景で説明したように、ここでの笑いには、「安堵をはじめとした、さまざまに重なる気持ち」が表現されていなければならない。
また、[Ⅲ]の前で「踊子への直接的なまなざしは表現できるが、」と相手に向けた内容が書かれているので、それとの対比で自分に向けた内容を入れるのが綺麗な流れになる。
これを踏まえて、「にこにこ」で表現できないものとして考えると、「自省というか、内観というか、とにかく、自分自身の気持ちの深まり」が適切である。
もっとも、各空欄の中では一番判断が難しいので、[Ⅰ][Ⅱ][Ⅳ]で判断して、[Ⅲ]は確認するだけという解き方が、実践的であろうか。
[Ⅳ]:ウ
[Ⅳ]の前後は、「これでは、瞬間的すぎる。[Ⅳ]が表現しきれていない。」となっている。
言い換えると、[Ⅳ]に入るのは、瞬間的すぎると表現しきれないものである。
もっと言い換えると、一定の時間を要するものである。
そこで、各肢を見ていくと、エの「気持ちの深まり」とウの「こみ上げてくる笑い」が、瞬間的すぎると表現しきれない、つまり本来は一定の時間を要するものである。
しかし、選択肢の組み合わせ上、エは絶対に入らない。
したがって、「自分でも押さえきれないほど、こみ上げてくる笑い」が入る。
この問題の成績
まだ、データがありません。